住所等変更登記の義務化と「スマート変更登記」
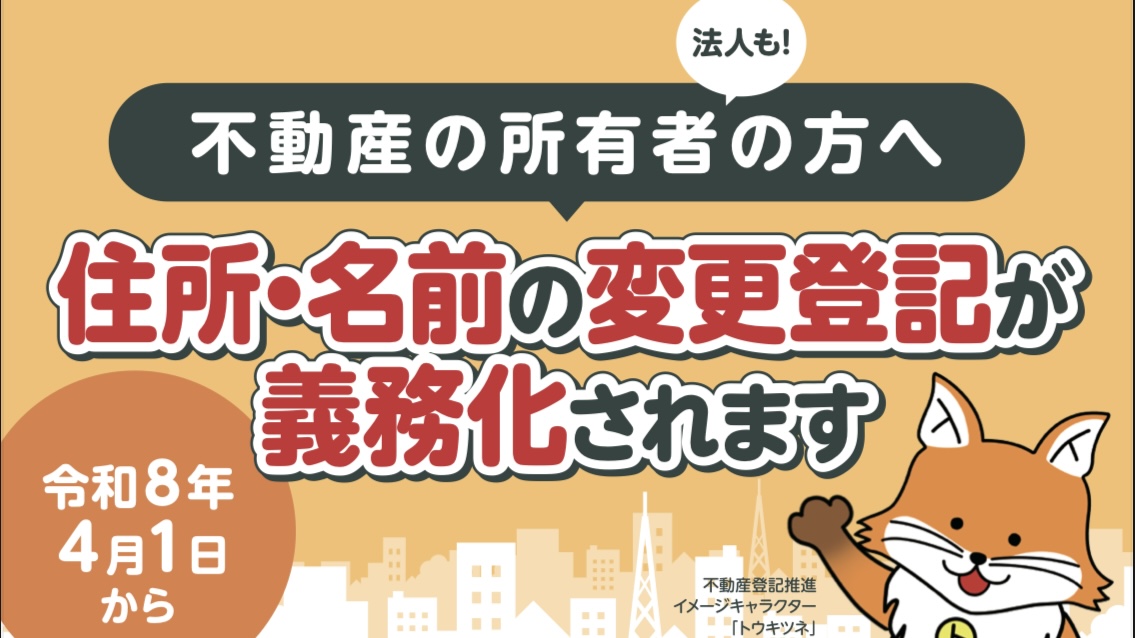
――令和8年4月1日施行、登記制度が大きく変わります
令和8年(2026年)4月1日から、「住所や氏名の変更登記」が義務化されます。
これまで「登記簿の名義上の住所が古いまま」「結婚・離婚などで名字が変わっても放置していた」というケースが数多くありましたが、今後は正当な理由なく変更登記を怠った場合、5万円以下の過料の対象となります。
すでに施行されている「相続登記の義務化」と並ぶ、大きな制度改革です。いずれも、社会的な課題である所有者不明土地問題の解消を目指したもの。
そして今回の改正では、新たに「スマート変更登記」と呼ばれる制度(登記官の職権による変更登記の仕組み)も同時にスタートします。
本記事では、制度の背景から具体的な内容、そして実務上の注意点までを、できるだけ平易に整理してご紹介します。
■ 1.なぜ「住所等変更登記」が義務化されるのか
所有者不明土地とは、登記簿を見ても「誰の土地なのか」「どこに連絡すればいいのか」が分からない土地のことです。
実はこの問題、国土の約2割(九州本島の面積より広い)に達するともいわれています。
原因のひとつが、「登記情報の更新がされていない」こと。
所有者が亡くなっても相続登記がされなかったり、転居しても住所変更登記をしなかったり――こうした小さな放置が積み重なり、結果として公共事業や災害復旧、都市計画の妨げになっているのです。
この状況を是正するために、国は二段階で法改正を進めています。
まず、相続登記の義務化(令和6年4月施行)。
次に、**住所等変更登記の義務化(令和8年4月施行)**です。
つまり、「名義人をきちんと登記簿に反映し」「その名義人の住所・氏名を最新の状態に保つ」ことが、法律上の義務になります。
■ 2.一般承継(相続)と登記の関係
――“取引時だけ”ではなく、“所有者すべて”の義務へ
これまで、不動産の登記情報を更新する必要が生じるのは、「不動産を売却・贈与・担保に入れる」など取引や処分を行うときが中心でした。
つまり、「動かさなければ特に問題なし」という認識の方が多かったと思います。
しかし、今後はそうはいきません。
たとえば――
- 被相続人(亡くなった方)の名義のまま放置している土地
- 旧住所のまま登記されている自宅
- 結婚で姓が変わったのに、登記簿は旧姓のまま
これらはいずれも、義務違反の対象になり得ます。
特に相続が発生した場合、「一般承継(包括承継)」と呼ばれるように、被相続人の権利義務は包括的に相続人に引き継がれます。
しかし登記簿上は自動で書き換わるわけではなく、**相続登記(所有権移転登記)**が必要です。
さらにその後、相続人の住所が変われば、住所等変更登記を申請しなければなりません。
つまり、不動産の「登記更新義務」は、
処分時の限定的な手続き → 所有者一般に広がった
という大きな転換を迎えたのです。
■ 3.スマート変更登記とは
――登記官の職権による変更手続き
住所や氏名が変わるたびに、全国の不動産所有者が登記申請を行う……。
義務化によりこの負担が一気に増えることは容易に想像できます。
そこで新たに導入されるのが、**「スマート変更登記」**という仕組みです。
これは、所有者が申請しなくても、登記官が職権で登記簿を変更できる制度です。
仕組みとしては――
- 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)やマイナンバーなどの行政データを参照し、
- 登記官が住所変更などの事実を確認できた場合に、
- 所有者の申請を待たずに変更登記を行う
という流れです。
ただし、誰でも自動で変更されるわけではありません。
スマート変更登記の対象になるためには、次に述べる「検索用情報の申出」など、事前の登録・同意手続きが必要です。
■ 4.検索用情報の申出とは
――スマート登記の前提条件
スマート変更登記を行うためには、登記簿上の所有者情報と、行政データを「ひもづけ」できる状態にしておく必要があります。
そのために設けられるのが、検索用情報の申出制度です。
● 自然人(個人)の場合
個人の場合、登記簿上の所有者が「自分で」次のような情報を法務局に申し出ます。
- 生年月日
- 連絡先(メールアドレス・電話番号など)
- 登記名義人のふりがな
これにより、法務局側が住民基本台帳ネットワーク上で本人を特定し、最新の住所を照会できるようになります。
● 法人の場合
法人の場合は、登記簿に会社法人等番号が登録されている不動産が対象です。
会社法人等番号によって商業登記簿と不動産登記簿のデータが連携し、所在地や商号の変更が自動的に反映される仕組みが整備されます。
こうした「検索用情報」が整っている不動産だけが、登記官による職権変更(スマート変更登記)の対象になります。
つまり、何の準備もしていない不動産はスマート変更登記の恩恵を受けられないという点に注意が必要です。
■ 5.スマート変更登記の運用イメージ
施行当初は、対象となる件数や範囲は限定的になると見られています。
たとえば、マイナンバーや住基ネット上で住所変更が確認できる個人の所有者から順次運用を開始し、データ連携の状況に応じて対象が拡大していく見込みです。
一方で、本人確認が難しいケースや、登記情報と住民情報に不整合がある場合には、従来通りの「申請による住所変更登記」が必要となります。
つまり、スマート登記は“すべてのケースを自動化する魔法の仕組み”ではないということです。
■ 6.罰則と実務対応
――5万円以下の過料の前に、やっておくべきこと
住所等変更登記を正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
「正当な理由」とは、例えば病気・災害・国外転勤など、やむを得ない事情があった場合などが想定されていますが、原則として「うっかり」「知らなかった」は理由になりません。
したがって、次のような準備を早めに進めておきましょう。
- 自分名義の不動産の登記簿(登記事項証明書)を確認する
- 住所や氏名に変更がある場合は、登記申請の準備を始める
- 相続未登記の不動産があれば、相続登記から先に行う
- 将来的にスマート変更登記の対象にしたい場合は、検索用情報の申出を済ませておく
不動産の名義が古いままだと、売却・贈与・担保設定などの取引にも支障をきたします。罰則だけでなく、実務的なトラブル防止という観点からも、早めの対応が大切です。
■ 7.進む登記制度のデジタル化
――“紙の登記”から“つながる登記”へ
スマート変更登記の導入は、登記制度のデジタル化・オンライン化の大きな一歩です。
法務局・自治体・他の官公庁の情報がつながり、所有者確認や登記の正確性をより効率的に確保する方向へ進んでいます。
将来的には、マイナンバーカードを活用したオンライン申請や、電子署名による本人確認もさらに進む見込みです。
不動産登記が、これまでの「紙ベースの手続き」から、「情報が連携する仕組み」へと進化していく流れの中にあることを意識しておきたいところです。
■ 8. 登記は“持ち主の責任”へ
- 令和8年4月1日から、住所・氏名の変更登記が義務化
- 怠ると5万円以下の過料
- 相続登記の義務化と並ぶ、所有者不明土地対策の柱
- 登記官が職権で変更できる「スマート変更登記」制度が同時にスタート
- ただし対象は、検索用情報が登録されている不動産に限られる
かつて登記は「取引のときだけ必要な手続き」でしたが、これからは「不動産を所有する者として当然に果たすべき責任」になります。
法改正は国の制度ですが、その実効性を支えるのは一人ひとりの行動です。
「自分の不動産の登記簿、ちゃんと今の住所になっているかな?」
――まずは、そこから確認を始めてみましょう。
【本日の一曲】
Diego Schissi Quinteto – Timba


