これからのAIとの向き合い方を将棋界から学ぶことができる
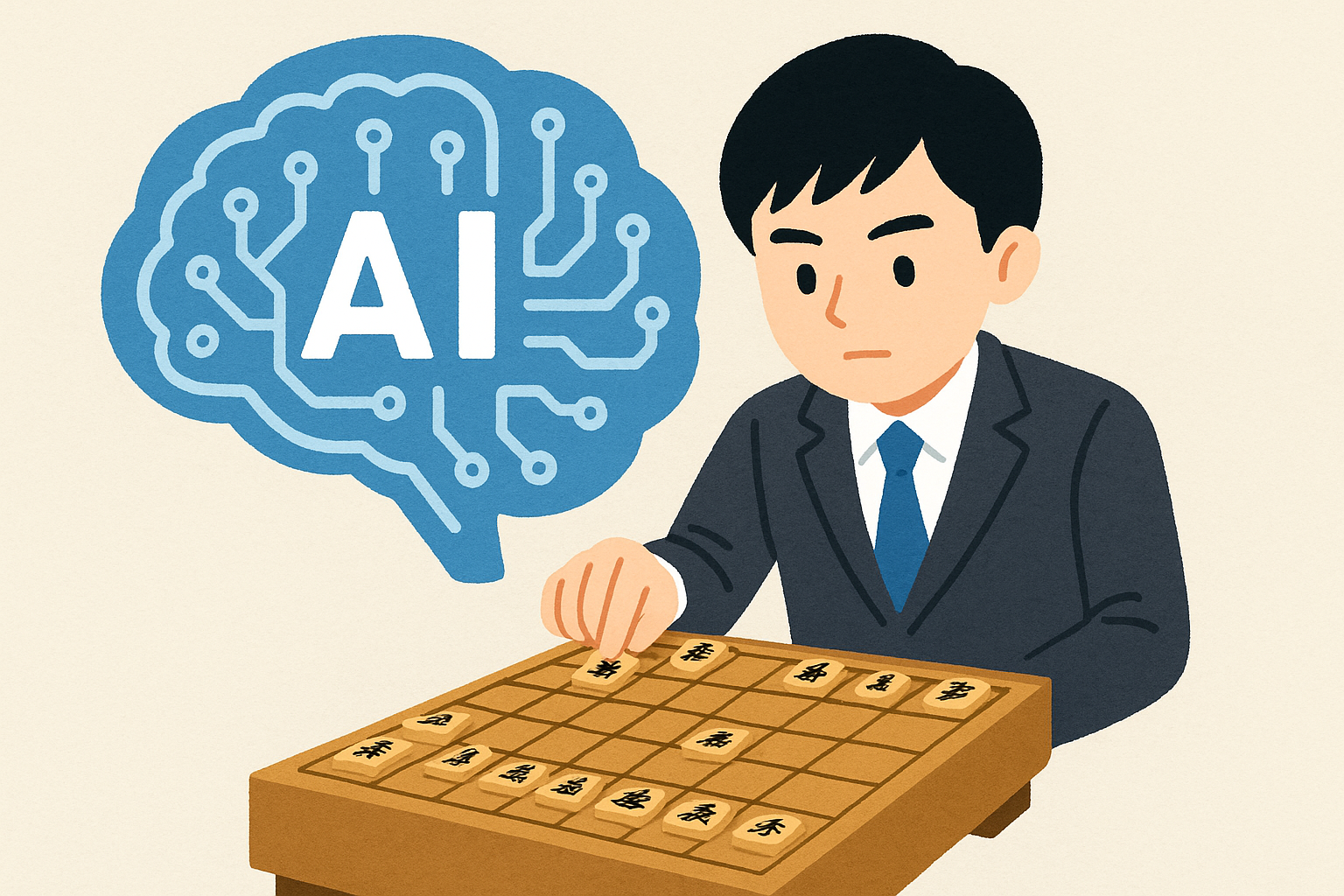
はじめに:なぜ「将棋界」がAIとの向き合い方の良い例か
AI(人工知能)は急速に進化し、ビジネス、教育、クリエイティブなどさまざまな分野で既に日常化しています。そんな中、「人間の価値はどう守るか」「AIをどう活用すべきか」という問いがいま改めて浮上しています。
その問いに対し、先んじて“AIに対峙”してきたのが将棋界です。プロ棋士がAIソフトに敗れた時期があり、「棋士の存在意義は?」という議論まで起きました。
しかしその後、棋士たちはAIを敵とせず、むしろ「パートナー」「道具」として取り込み、より高みを目指す形へと変化しました。今回はそのプロセスを振り返りながら、私たちがAI時代に備えるヒントを探ってみます。
1.AIに勝てない、でも消えるわけではない――将棋界の転機
10年ほど前から、将棋ソフト(AI)がプロ棋士を上回る力を持つようになりました。これにより「人間の棋力ではAIに勝てないのでは」「棋士という職業が不要になるのでは」という不安が将棋界にも広がりました。
例えば藤井七冠は、「AIの実力が棋士をしのぐようになった10年前から活用しています。強くなるためのパートナーという感覚」という言葉を残しています。
ここで重要なのは、「勝てない」と知った瞬間に終わるわけではなく、むしろそこから新しい活用・共存の道を模索したことです。
この教訓は、私たちの仕事・生活においても同じです。AIに「奪われる恐れ」を感じて立ち止まるのではなく、AIを「どう活かすか」「どう共に価値を創るか」を考えるフェーズに入っているのだと思えます。
2.AIを「敵」から「パートナー」へ:将棋界の変化
将棋界では、AIを「敵」として戦うのではなく、むしろ「共に高め合う存在」と捉えるようになりました。記事では「AIが『敵』から『パートナー』へ」変化した――と紹介されています。
たとえば、序盤の定跡研究、中盤・終盤の読み、形勢判断などにAIが“示唆”を与え、その知見を棋士自身が自分の直観・経験と照らし合わせながら活用しているというのです。
藤井七冠はこう述べています:「人間的な感覚ではなかなか考えづらい指し方や形勢判断、大局観に触れることができるので、総合的な判断力を高めるうえで非常に効果があった。ただし、AIが示す情報を無批判に受け取ってしまうと、自分自身の思考力がかえって落ちてしまうリスクもある」
要するに、AIを使うということは「AIに任せきりにしない」「自分の思考を放棄しない」ことも含まれているのです。
この構図は、ビジネス・教育・クリエイティブなどの分野にもそのまま当てはまると思います。AIを導入する時、「まずは目的を明確に」「自分(人間)の強みを活かしつつ」「AIの知見を取り込む」というプロセスが肝要です。
3.“使って・挑戦して・振り返る”というループ
将棋界では、AIの提示する最善手・形勢判断を分析し、それを自分の対局に取り込んだうえで「この手がどうだったか」「自分はどう考えたか」を振り返る作業が重要とされています。佐々木八段は、「研究して、対局で実際にやってみて、後でそれを振り返る」と語っています。
この「研究→実践→振り返り」のサイクルが、AIを活用して知見を深め、自分自身を成長させる鍵なのです。
ビジネスの現場で言えば、AI導入後も「振り返り」がないと、ツール化しただけ・導入しただけで終わってしまいます。
例えば、AIが示した分析をそのまま適用しても、なぜその結果が出たのか、自分の判断とどう違ったのかを考えなければ、自分の思考力は育ちません。将棋界の言葉を借りれば、「AIが示した手をそのまま指すだけでは、自分の“読み”や“直観”は培われない」のです。
4.“未知の局面”で価値が出る、人間の存在意義
将棋でいう“終盤”は、定跡が通用しない未知の局面=“カオス”の領域です。藤井七冠は、「いくら事前に研究していても、絶対にどこかで未知の局面になります。一番重要なのはその局面でどう考え、どう対応するか。その力をつけるためにAIを使うということ」だと語っています。
つまり、定型化できる部分(序中盤・定跡)はAIに近づけても、最終的な勝負どころ、創造力・直観力・読みの深さといった“人間性”が問われる部分は、やはり人間にこそ価値がある、というメッセージです。
これは私たちがAI時代に生きるうえで大きな示唆になります。
- ルーチンワーク・定型作業はAIが代替可能となる。
- しかし「未知の課題・イノベーション・価値創造」の部分では、人間の直観・感性・判断の余地が残る。
将棋界が示しているのは、「AIに任せるところ」と「人間が考えるところ」を区別し、後者を意識的に磨くことの重要性です。
5.これから私たちが取るべき「AIとの向き合い方」4つの視点
将棋界の実例を参考に、私たちが今後取り組むべき視点を整理します。
① 目的設計:AIを“使う目的”を明確にする
将棋界では「強くなるため」「読みの幅を広げるため」にAIを使っています。
私たちも「生産性を上げたい」「新しい価値を創りたい」「判断の質を高めたい」といった目的を明確にし、AIを手段として使うことが重要です。
② ツールとの関係性を意識する:AIを“パートナー”として使う
AIを“敵”や“代替”と捉えると恐怖や抵抗が生まれます。しかし将棋界はAIを“パートナー”として捉え直しました。
私たちも、AIを道具として使いこなすのではなく、共に働く“仲間”として関係を築けると、可能性が広がります。
③ 自ら考える力を維持・強化する
将棋界では「AIが提示する手を無批判に受け入れず、自分で考え、判断し、振り返る」ことを重視しています。
私たちも、AIが出した答えをそのまま使うだけではなく、「なぜこの答えなのか」「自分ならどうするか」を常に問い続けることが必要です。
④ 人間らしい価値に注力する ― 未知・創造・感性
AIが得意とするのは大量データ処理・最適化・パターン認識ですが、人間が得意とするのは“新しい発想”“直観”“価値観に基づいた判断”です。将棋で言う「終盤の読みの深さ」にあたる部分です。
仕事でも日常でも、ルーティンをAIに任せて、人間は“未知”に備え、創造と関係構築に注力できると強みになります。
6.将棋界の事例からみる実践ポイント
将棋界の具体的なエピソードをいくつか振り返り、私たちの行動に落とし込んでみましょう。
- 定跡研究:AIソフトが提示する数千の手筋を調べる。→ ビジネスでは「AI分析から得られた知見を学び直す」
- 実戦:実際の対局で試す。→ 仕事で言えば「AIが出した企画/分析を実行してみる」
- 振り返り:指した手・AIの予測との差・自身の判断を振り返る。→ プロジェクト終了後に「AIの提案 vs 自分の判断」「差が出た理由」をレビュー
- 未知の局面:定跡が効かない終盤で勝負。→ 新規事業・未知のマーケット・複雑な人間関係に挑む場面こそ人間の価値が問われる
特に、「AIが示した“最善解”を受け入れただけでは、自分の力は伸びない」という藤井七冠の言葉は重いです。
つまり、AI活用とは「使い方」を学ぶことであり、「自分をどう拡張するか」が鍵なのです。
7.AI時代における「棋士⇔私たち」の共通テーマ
将棋という盤上の世界は、非常に限定されたルール・領域ですが、だからこそ「人間とAIの関係性」を鮮明に映し出します。以下、私たちの日常・業務に落とし込んだ共通テーマです。
- 学び続ける姿勢: 棋士たちはAIを使って自己研鑽を続けています。私たちも、AIが示す知見を受動的に使うのではなく、「次にどう活かすか」を考え続ける必要があります。
- 自己判断力の育成: AIの結果・提案を鵜呑みにするのではなく、自分の判断・直観・価値観を混ぜて意思決定する。
- 役割の再定義: ルーティン化された業務はAIに任せ、私たちは“創造”“人間関係”“未知の領域”を担う。
- 絶えず未知に挑む: 定型化された業務・知識には限界があります。将棋界が終盤の読みを極めるように、私たちも「未知の局面」「変化の激しい場」に挑む態度が問われます。
- 協働と補完: AIは人間の敵ではなく補完者。人間が持つ“目的”“価値”“人間関係構築”をAIと共に作るパートナーとして使う。
8.私たちの“これからの行動”に向けて
では、具体的に私たちが今からできることを整理します。
- 目的を明確にする: AI導入・活用を検討する際、「何を変えたいのか」「どこで価値を出したいのか」を言語化する。
- 使い方を設計する: AIは万能ではありません。どのプロセスをAIに任せ、どの部分を自分が手掛けるかを設計する。
- 実践 → 振り返り: AIから得られた提案を使った後、振り返りの時間を設け「どうだったか」「何が改善できるか」を分析する。
- 未知に投資する: 定型化された成果ばかりを追うのではなく、「新しいチャレンジ」「創造的な仕事」「人間ならではの価値が問われる場」に注力する。
- 学び続ける文化を作る: 将棋界のように、AIを取り入れた学びの習慣を組織・個人に根付かせる。
まとめ:AIとの「共存」がこれからのキーワード
将棋界の事例から学べるのは、AIを“倒すべき敵”とするのではなく、“共に価値を創るパートナー”と捉え、自分自身の思考力・判断力・創造力を磨き続ける姿勢です。
AIにできることを任せ、人間だからこそできることに集中する――それが、これからの時代における“勝ち筋”ではないでしょうか。
私たちは今、AIという強力な“知の道具”を手にした時代に生きています。
その道具を使いこなすだけでなく、自分自身の考え・価値・判断に磨きをかけることこそが、将棋界が示した「良い向き合い方」なのだと思います。
ぜひこの機会に、自分なりの「AIとの付き合い方」を設計してみてはいかがでしょうか。
◻︎◻︎出典:PRESIDENT Online 『そりゃ圧倒的に強いわけだ…「あなたにとってAIとは」という質問に藤井聡太七冠が返したさすがの回答』
https://president.jp/articles/-/103673
【本日の一曲】
Rick James – Mary Jane


