贈与税非課税枠110万円 × こどもNISA
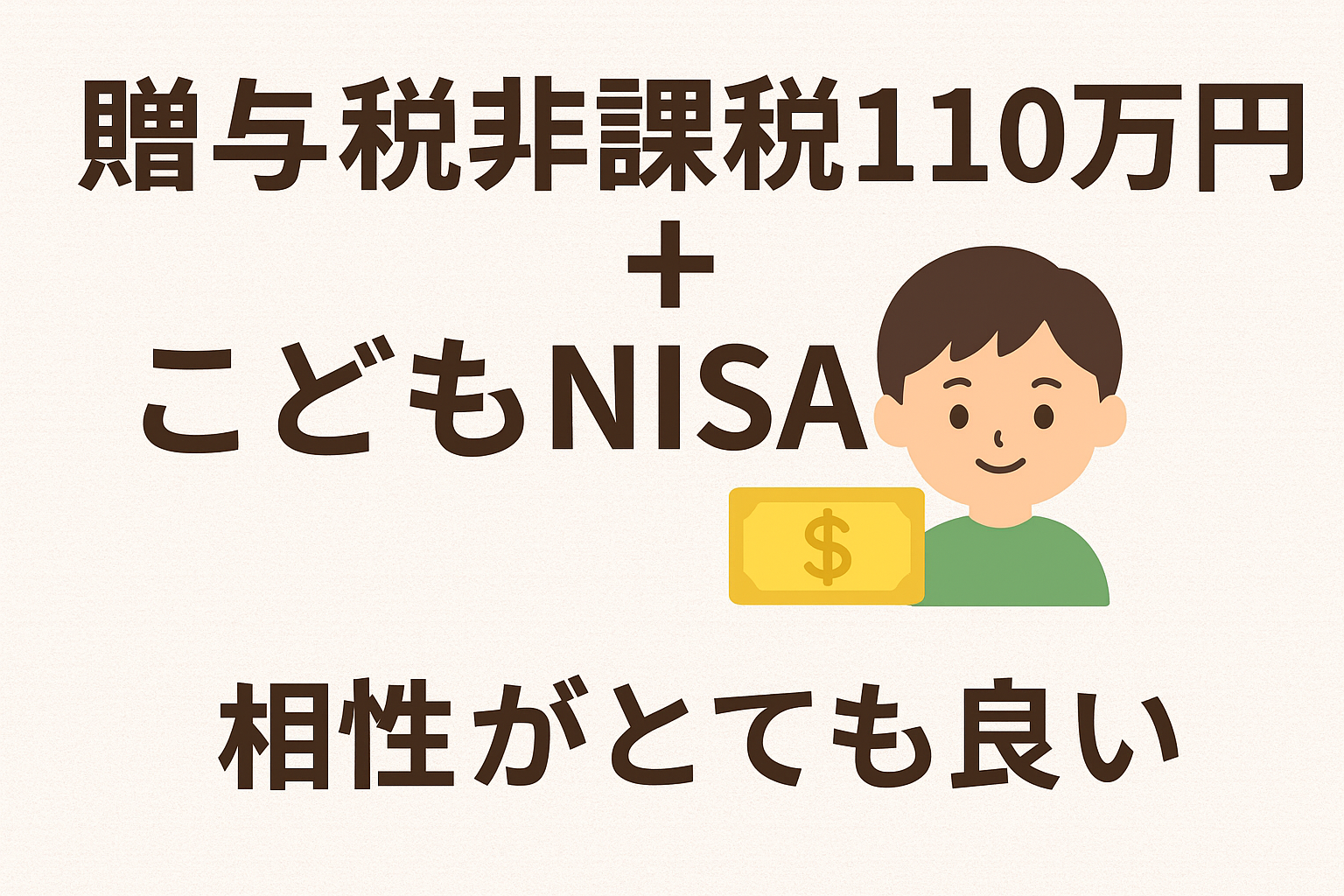
― 家族の未来にやさしい“資産のバトンリレー” ―
不動産を扱っていると、「子どもや孫の世代に、少しずつでも財産を残しておきたい」と考えるお客様はとても多くいらっしゃいます。
家や土地などの「形ある資産」だけでなく、お金の面でも上手にバトンを渡す方法があります。
その代表的な仕組みが「贈与税の非課税枠(年間110万円)」と、2026年に新しく始まる「こども支援NISA」。
この2つをうまく組み合わせると、税金の負担を抑えながら、次の世代の資産形成を応援できるとても良い仕組みになります。
(※この記事は税理士によるアドバイスではなく、不動産に関わる暮らしの情報としてお伝えしています)
1. 贈与税の非課税枠とは?
まずは、「贈与税の非課税枠」から見ていきましょう。
親や祖父母が子ども・孫にお金を渡すとき、その金額が一定を超えると「贈与税」がかかります。
ただし、年間110万円以内であれば税金はかからず、申告の必要もありません。
これは「暦年課税」と呼ばれる仕組みで、毎年1月1日〜12月31日までの間に、受け取った合計が110万円以内ならOKというルールです。
たとえば、
- お子さんに毎年100万円ずつ10年間贈与した場合
→ 合計1,000万円を、非課税で移転できます。
しかも、このお金は相続のときには基本的に親の財産に含まれません。
つまり、「少しずつ贈与しておく」ことで、相続税の負担を軽くする効果もあるんです。
2. 「3年」→「7年」に延長された“生前贈与加算”
ただし、注意しておきたいポイントがあります。
贈与してからすぐに相続が発生すると、その贈与は「なかったこと」にされて、相続財産に戻される仕組みがあるのです。
この期間が、以前は「3年」だったのですが、2024年からは“7年”に延長されました。
つまり、相続税対策として生前贈与を考えている方は、できるだけ早くスタートすることが大切です。
贈与を「節税目的だけ」で考えると難しく感じますが、
「子どものために教育資金を少しずつ渡しておく」
「孫の口座に将来のためのお金を積み立てておく」
と考えれば、より自然な形で続けやすいと思います。
3. 2026年から始まる「こども支援NISA」とは?
次に、いま注目を集めている「こども支援NISA」について。
これは、かつて存在した「ジュニアNISA」の後継制度として、2026年度のスタートを目指して準備が進められています。
NISAとは、投資で得た利益(運用益や売却益)に税金がかからない制度。
通常なら約20%の税金がかかるところを“非課税”にできるため、資産形成を応援する制度として人気を集めています。
これまでは大人向け(18歳以上)だけでしたが、
「こども支援NISA」は、子どもの将来のための投資も応援する仕組みになります。
4. 「ジュニアNISA」との違い
旧制度の「ジュニアNISA」は、途中で引き出しができないなど使いにくい点がありました。
そのため、多くの家庭では口座を作ってもあまり利用されませんでした。
それに対して「こども支援NISA」では、
- 教育資金などが必要なときには途中で引き出せる
- 年間投資枠も80万円→120万円に拡大される見込み
- 生涯非課税枠(大人のNISAと同じく最大1,800万円)も活用可能
といった、より柔軟で使いやすい制度になる見通しです。
5. 贈与とNISAを組み合わせるとどうなる?
ここからが今回の本題です。
この「贈与税の非課税枠」と「こども支援NISA」を組み合わせると、非常に効率の良い資産移転が可能になります。
たとえば――
- おじいちゃん・おばあちゃんが、孫のために年間110万円を贈与。
- そのお金をこども支援NISA口座で運用。
すると、
💡 贈与時も非課税、運用益も非課税。
つまり、「もらうとき」も「増えるとき」も税金がかからない、という“最強コンビ”です。
6. 長期で見れば「お金の教育」にも
たとえば、生まれたばかりのお子さんに毎年100万円を贈与して18歳まで積み立てた場合、
贈与額は合計1,800万円。
これをNISAの非課税枠内で運用すれば、仮に年3〜5%で運用できた場合、
18歳の時点では2,500万円以上になる可能性もあります。
もちろん投資なのでリスクはありますが、
一方で「お金が働く」仕組みを子どものうちから見せてあげることも、
将来の金融教育として大きな意味があります。
伝説の投資家・村上世彰さんも、
子どものころに父親から「100万円を渡されて株の勉強をした」という話があります。
お金の価値やリスクを早いうちに体験できるのは、何よりの“生きた教育”になるでしょう。
7. 「土地・不動産」とのつながり
贈与やNISAというと「お金の話」のように聞こえますが、
実は「土地」や「不動産」をお持ちの方にとっても大切なテーマです。
不動産は現金と違って分けにくい財産。
そのため、相続のときにトラブルになりやすい面があります。
だからこそ、一部を現金化して少しずつ贈与しておくことで、
次の世代が困らないように備えておくことができます。
また、不動産を売却した資金の一部を「こども支援NISA」で運用するのも良い方法です。
土地や建物という“動かない資産”と、NISAのような“運用できる資産”をバランスよく組み合わせることで、
家族全体の資産をより柔軟に守ることができます。
8. 今からできる準備
「こども支援NISA」はまだ制度設計の段階ですが、今からできる準備もあります。
- 毎年の贈与記録を残しておくこと
→ メモ書きでも良いので、「○年○月○日、○万円贈与」と残しておくと安心です。 - 子ども名義の銀行口座をつくること
→ 実際にお子さんの名義にお金が入る形が理想です。 - 家族で“お金の話”をすること
→ 「どうして贈与するのか」「どんな使い方をしてほしいのか」を話すことで、家族の理解が深まります。
9. おわりに
贈与税の非課税枠(年間110万円)と、2026年スタート予定のこども支援NISA。
この2つをうまく使うことで、税金の負担を抑えながら「家族の未来」に備えることができます。
お金の話は少し難しく感じますが、
要するに「少しずつ・早めに・計画的に」動くことが大切です。
せとうち不動産では、不動産の売買や相続に関するご相談だけでなく、
こうした「家族の資産を守る考え方」についても丁寧にお話ししています。
“次の世代へ、やさしく資産をつなぐ”
その第一歩として、贈与とNISAの仕組みを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。
(執筆:せとうち不動産)
※本記事の内容は一般的な制度説明であり、税務判断を行うものではありません。具体的な税金の取り扱いについては、税理士などの専門家にご相談ください。
◻︎
【本日の一曲】
Richard Beirach · George Mraz · Jack DeJohnette – Snow Leopard


